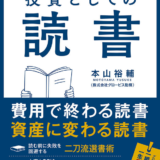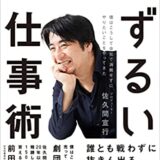「一般社員であっても経営者目線で考えるように」と新入社員時代に言われた方も多いのではないでしょうか?私もMBAを勉強したので、高い視座で物事を考えた上で、具体的なアクションとの整合性を考えることの利点は分かります。
ただ、経営者目線で考えることと、机上の空論は紙一重だなと思う場面が多いです。頭でっかちに考えても、成果にはつながりません。
具体的に経営者目線で考えるとはどういうことかモヤモヤしていたのですが、つい先週、経営者ばかりが集まる会があり、経営者目線ってこういうことかぁと膝を打つ出来事がありました。それはあとつぎ会議という、グロービス経営大学院の卒業生や現役の受講生で、事業承継の人だけが参加できるイベントで、120人の枠が一瞬で満席になり、参加者のほとんどは経営者というそんな特殊な空間でした。
たくさん学びがあったのですが、その中で、個人的にどのレイヤーの社員でも、意識することで一段高い視座に立ち、具体的な施策につなげやすいと感じたポイントを厳選して3つお伝えします。
動作につながるKPI設定
一つ目は現場社員が前向きになるためのKPIを考えるです。岩手県にある、200年近く続く旅館「湯の杜ホテル志度平」の久保田社長から学んだ内容です。
これまでは売上や利益を数値目標にしていたのですが、従業員の様子を見ていると自分達の仕事がどうその数字に結びついているのか、いまいち自分事として捉えにくいように感じたそうです。
そこで、NPS(どれだけ周りの人に紹介したいか)や旅行サイトの満足度スコア、リピート率など、アクションと紐づくKPIに変えました。それによって自然と従業員から「今日のじゃらんのスコア昨日より上がってますね」など、自然と声が上がるようになったようです。
ここで大事なことは、メンバーのことをしっかり観察することです。どんなことに興味があり、モチベートされるのかを見極めるためにも、普段からのコミュニケーションが大切になります。さらにお客様からのお礼の手紙などはスピーディに共有しているそうです。モチベーションスイッチの場所を把握しているからこそのアクションを考える必要があります。
また、抜け道のないKPI設計も大切になります。インドの笑えない笑い話で、毒蛇の話があります。
毒蛇を規制するためのKPIが毒蛇を増加させた
昔、インドで毒蛇が多く生息していることから、毒蛇を捕まえた者に賞金を出す制度を政府が創ったそうです。
すると、真面目に毒蛇を捕まえる人だけでなく、毒蛇を育てて、それをお金に替える悪い人も出てきました。政府は見かねて、この制度を取りやめたところ、毒蛇を飼っていた人が一斉に毒蛇を町に解き放ち、むしろ毒蛇が増えてしまったという話です。
個人的に性善説で制度やKPIは設定したいと思いますが、抜け道がないか?は気にした上で設定する必要があります。
気づくと思考の幅は狭くなる
二つ目は思考の自由度を広げるです。
ブラックサンダーの河合社長は、どんな企画でも提案OKな空気感を作っているとおっしゃっていました。確かにブラックサンダーと言えば、一眼で分かる義理チョコのキャッチフレーズや、バレンタインデー企画として下駄箱も商品化するなどユニークで自由な印象があります。
社員の立場からすると企画を考えやすいですし、なおかつ提案すること自体が楽しくなってしまいそうです。
その背景には、河合さん本人がマーケティング部を設立し色んな施策を展開してきたからこそ出来上がった文化だと私は感じました。
もちろん企業それぞれのブランドがあるので、何でもかんでも自由にはできませんが、意識的に自由度を広げないと気づくと凝り固まってしまうものです。
私も現在、ビジネススクールのSNSのプロジェクトリーダーをしている中で試行錯誤中の身ではあるのですが、色んなSNSのチャンネルを見て、これまでやったことないけど面白そうと思ったものを配信する過程で、メンバーからもさらに新しいアイデアが集まっている感覚があります。
幅広く情報を集め、小さく社内でアクションをすることで少しずつ施策に幅が出てきます。
ミシン愛が人を動かす
最後3つ目は自社サービスを愛するです。
先日ガイアの夜明けにもご出演されていた、子育てにちょうどいいミシンやTOKYO OTOKOミシンでも有名なアックスヤマザキの山崎社長がおっしゃっていた言葉です。
山崎さんは心からミシンのことが大好きで、職場でもミシンについて気になったことがあると、すぐにメンバーと雑談してしまうそうです。
これが段々とメンバーにも伝播し、皆が自社の製品を誇りに感じます。とあるご高齢の社員の方はかなり大きなご病気をされた後も週に1回で良いから働きたいとお願いをされて、山崎さん本人も驚いたと言っていました。
さすがに入社したての社員がここまでの自社への愛を育むのは難しいです。ただ、自社サービスのことを理解して、可能な限り利用してみて、一部だけでもここは良いなと思うところを見つける努力はできると思っています。無理に好きになる必要は全くないですが、プロとして自社サービスの理解は極めたいですね。
これは完全に余談ですが、ちょうど一昨日お笑いコンテストR1グランプリ2023で優勝した田津原理音さんはアックスヤマザキで週に3回ミシン点検の仕事をしており、放送日も3/4のミシンの日でした。山崎さんは当日少しお話しさせていただいたのですが、とても気さくで面白い方で、やはりそんな面白い社長のいる面白い会社には面白い人材が集まるのだなとしみじみと感じました。
まとめ
というわけで、今日は経営者目線で考えるためにできるアクションをお話ししました。メンバーを動かすKPI、思考の自由度を広げる、自社サービスを理解して好きになるの3つをお伝えしました。
粒度はそれぞれ異なりますが、一段視座の高いアクションにつながりますと幸いです。