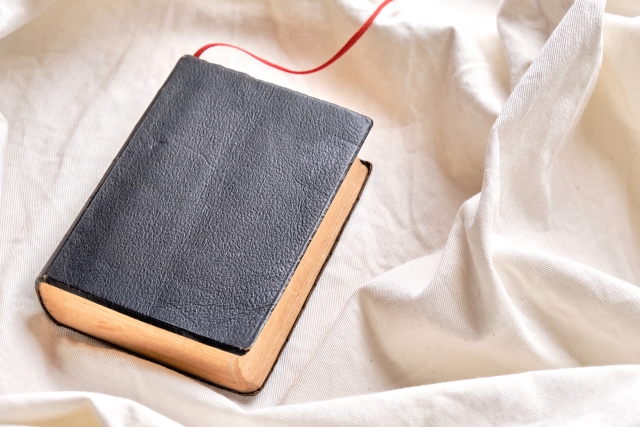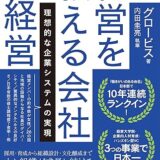今回は読書習慣を身に着ける方法について考えます。
ビジネスパーソンの方と会話の中で「もっとたくさん本を読まないとと思っているんですが中々習慣化できない」と聞くことがしばしばあります。
2024年の目標の一つに読書を掲げた方も多いのではないでしょうか?
私自身、今でこそ年間100冊読むようになりましたが、社会人になった当初は年間数冊程度しか読んでおらず、同じように本を読んだ方がいいとは思いつつも中々できずにいたのでこの気持ちはよくわかります。
私も読書に対しては努力しないと大量には読めないという意味で、まだまだなのですが、一定期間本を読まないとむず痒くなるようになってきたことから習慣化には成功している感覚があります。
読書と動画学習の違い
実際に年間100冊読んでみるとかなり費用対効果の高い投資だなぁと日々実感します。
読書はインプットですが、動画視聴と違って読み手に解釈する領域、つまり考える余白があります。
荒木博行さんの書籍「自分の頭で考える読書」にも読書には余白を考えるからこそ動画学習とは違う筋肉を鍛えることができ、今の時代に必要なことと記載があります。
知識を詰め込むだけではないので、動画視聴と違ってやや抽象度を高める思考力を鍛える訓練になり、抽象度を高めてから具体に落とし込むので活用範囲も広がります。
また個人的な意見ですが、ある程度の読書量をこなさないと見えない世界があるのではないかと思っています。
chat GPTも一定のデータ量を超えたあたりから爆発的に進化したのと同じかなと思っています。
ポートフォリオ読書
では仕事やプライベートで忙しく、読書習慣がない人がどうやって習慣的に本を読めるようになるのか、その方法について考えていきます。
速読や全部読まずに必要なところだけを読む方法など、一冊あたりにかける時間を短くする方法についての書籍はたくさんありますが、個人的に慣れないうちはこの方法は効果が薄い気がします。
私も数年前に年間10冊ほどしか読まない時に実際に試しましたが本の内容が全然頭に残らなかったです。
なので、読書習慣が身につく前はすべてのページに目を通して一定の文章量を読み「読書体力」を地道につけることをおすすめします。
ただ、いきなり分厚い書籍や難解な書籍ばかりに挑戦するのはハードルが高いです。
そこであなたなりの読書のポートフォリオを組むことをおすすめします。
言い換えると読書のモチベーションを上げることを目的にして、モチベーションを継続させるために自分なりに手持ちの本のカテゴリーを考えます。
例えば私の場合は次の3つにカテゴライズしています。
①血肉化読書
一つ目は仕事のアウトプットですぐに必要な本です。
必要に駆られて読む本は、すぐにアウトプットにつながるので恥肉化しやすく、成果にも繋がりやすいことから読書へのモチベーションが高まりやすいです。
私であればSNSのプロジェクトリーダーをしている時に読んだSNSの本や、最近は新しくメンバー育成のためのコンテンツを作っている関係で育成やリーダーシップに関する本は前のめりに読めましたし、かなり頭にも残っています。
②レコメンド読書
二つ目はおすすめされた本です。
知人や自分が尊敬する著名人がSNSなどで紹介する本、書店で気になった本がこれにあたります。
私は誰かに本をおすすめされたら、すぐにAmazonで書籍を買うようにしています。
最初のうちは自分からおすすめ本を聞いてみるのも良いです。その際になるべく、尊敬する上司や上司の上司、先輩など身近な目上な方に聞いてみます。聞いたからにはある程度早く読まないとと前のめりに読書することができます。
と、ここまでの二つはやや強制感を持たせて自分を読書に取り組ませるスタンスでしたが、この方法だけだと習慣化する前に息切れしてしまう危険性があります。
③ハートフル読書
そこで三つ目は心を豊かにする本を選びます。
例えば、エッセイや短歌や俳句などの書籍です。
私は詩人の俵万智さん坂村真民さん若松英輔さんが好きで、年間読む100冊のうち10冊はこういったジャンルの本を選んでいます。
読んだ内容をすぐにアウトプットに繋げるのではなく、時間軸を長期に変えたり、ゆるやかな時の流れを作ることができ、慌ただしい生活の中にゆとりをつくることができます。
また、副次的効果ですが、短歌や詩集などは30分ぐらいで読めるため、1冊本を読んだということがその日の充実感につながり、また本を読み続けるモチベーションにつながります。
まとめ
というわけで今回は読書を習慣化するための方法についてポートフォリオを組むことをお伝えしました。
あなたの好みに合わせた組み合わせを考えるきっかけになりますと幸いです。
最後に読むと読書がしたくなるおすすめ本をご紹介します。
- 浅田すぐる 「早く読めて、忘れない、思考力が深まる 「紙1枚!」読書法」
- 本山裕輔 「投資としての読書」
- 落合陽一「忘れる読書」
2024年もどうぞよろしくお願いいたします。